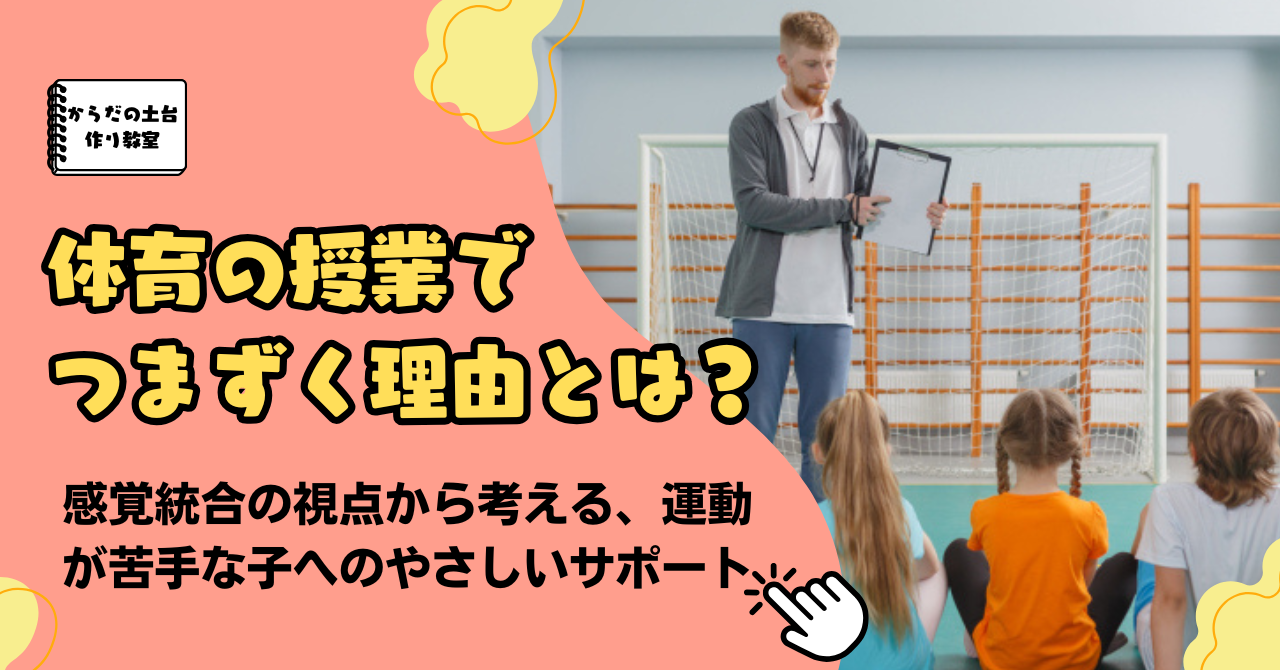感覚統合の視点から考える、運動が苦手な子へのやさしいサポート
はじめに:体育の授業が「つらい」と感じる子がいます
「体育になると、表情が曇る」「できないことが恥ずかしくて隅にいたがる」――
そんなお子さんの姿を見たことはありませんか?
小学校の体育は、子どもたちがさまざまな体の動きを経験する大切な授業。でも実際には、「できない」「こわい」「みんなと違う」と感じ、つまずきを抱える子が一定数います。
この記事では、「体育の授業でつまずく理由」について感覚統合の視点から解説し、運動が苦手な子でも“ちょっと楽しめる”ようになるためのヒントをご紹介します。
1. 体育が苦手に見える子どもたちの特徴
体育の時間にこんな様子はありませんか?
- マット運動で体がうまく丸められない
- 鉄棒で手を離すのが怖い
- 跳び箱のタイミングが合わずぶつかってしまう
- ボール運動で動きがぎこちない、よけられない
これらの「できなさ」には、感覚や身体の発達段階が大きく関係していることがあります。
2. 感覚統合の視点から見る「つまずき」の理由
「運動が苦手」と感じる背景には、感覚統合のバランスがまだ整っていないことが関係している場合があります。以下の4つは特に体育の授業で影響が出やすい要素です。
● 前庭覚(ぜんていかく)
体のバランスやスピード・方向の変化を感じ取る“バランスセンサー”のような感覚です。

前庭覚が未熟だと:
- 回る・ジャンプ・高い所が苦手
- 体育で動きがぎこちない、転びやすい
遊びの中で育てる:
ブランコ、回転イス、前転、ジャンプ遊びなど
● 固有受容覚(こゆうじゅようかく)
手足の位置や動き、力加減を無意識に感じ取る感覚です。

固有受容覚が弱いと:
- 力加減がわからず、手をつく・足を蹴る動作がぎこちない
- 鉄棒や跳び箱などで「体がうまく使えない」と感じる
育てるには:
動物歩き、引っ張り合い、押し相撲、雑巾がけなど全身を使う活動
● ボディイメージ(身体図式)
自分の体がどこにあって、どんなふうに動いているかをイメージできる力です。

ボディイメージが弱いと:
- 動作の「コツ」がつかみにくい
- 跳び箱やマット運動で、空間の使い方がうまくいかない
● 運動の協調性(タイミングやリズム)
全身の動きをうまく連携させるための力です。

協調運動が苦手だと:
- 両手両足がバラバラに動いてしまう
- タイミングがずれて転びやすい
3. よくある体育の種目別つまずきとサポート方法
◯ マット運動(前転・後転)
よくある困りごと:
・手をつく位置が分からない
・体を丸める感覚がつかめない
サポートのヒント:
・まずは「ゴロゴロ転がる遊び」から始める
・段ボールトンネルくぐりで丸くなる感覚を体験
◯ 鉄棒
よくある困りごと:
・ぶら下がると怖くて手が離せない
・回る感覚が気持ち悪い
サポートのヒント:
・はじめは「腕だけで支える」遊びから
・低い鉄棒でのぶら下がり時間競争などから慣れていく
◯ 跳び箱
よくある困りごと:
・踏み切りのタイミングが合わない
・体が前に出ずにぶつかってしまう
サポートのヒント:
・縄を飛び越えるなどジャンプ遊びで踏切動作を強化
・マットの上にクッションを重ねた台でジャンプ練習
◯ ボール運動(キャッチ・投げる・よける)
よくある困りごと:
・ボールがうまく見られずキャッチできない
・反応が遅れて当たりやすい
サポートのヒント:
・風船や大きな柔らかいボールを使ってゆっくりした動きで練習
・「転がってくるものをよける」ゲームからスタート
4. 体育は“できる”より“楽しめる”がスタートライン
体育の授業は、全員が「完璧にできる」ことを求める場ではありません。
えいと運動教室でも大切にしているのは、「できた!」よりも「楽しかった!」「やってみたい!」という気持ちです。
ちょっとしたサポートで、「あ、やれたかも」「怖くなかった」が増えていけば大丈夫。
感覚統合の視点を知ることで、「できない理由」が「できるチャンス」になります。
まとめ:できない理由を“わかる”と、寄り添える
体育が苦手に見える子には、必ず背景があります。
その一歩奥にある感覚のズレや不安に気づけたとき、サポートの方法もグッと広がります。
保護者の皆さんが「うちの子には、どんな感覚が育っているのかな?」と興味をもって見守ること。
それが、何よりも子どもを安心させ、次の「できた!」につながっていきます。
参考文献・引用元一覧
- 感覚統合と運動の教科書(子どもの「できない」に寄り添う発達支援)
監修:山岡 昌和、出版:合同出版
→ 感覚統合(前庭覚・固有受容覚・身体図式など)に関する基礎的な情報に基づき記述しています。 - NCBI(National Center for Biotechnology Information)
→ 前庭覚・固有受容覚の神経科学的な働きや、運動との関係性についての学術論文を参考にしています。
(例:Vestibular function and motor control in children) - Sensory Processing Disorder Foundation
→ 感覚統合と運動の関連、遊びの重要性についての海外専門サイトより引用。
(例:Sensory integration and movement strategies) - Chicago Occupational Therapy
→ バランス感覚や感覚統合を高めるための遊びのアイデアを参考にしています。
(例:Vestibular activities for kids) - NOTE・Hanayou・Kyoiku.sho.jp 他の国内教育系サイト
→ 小学生の体育やリレーに関する実例、支援の工夫事例を参考に構成しています。