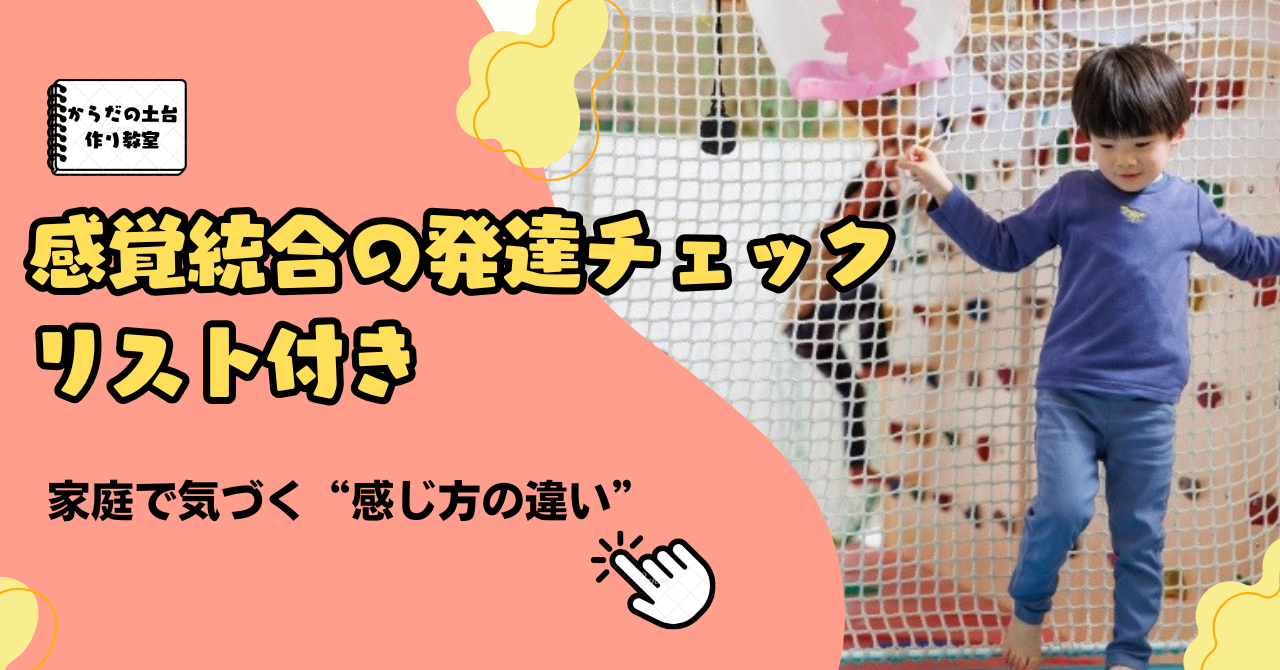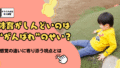はじめに|「運動が苦手」は感覚のせいかもしれません
「うちの子、なんでこんなに転ぶんだろう…」「苦手なのは性格?それとも発達の問題?」
そう思ったことはありませんか?
もしかすると、それは“感じ方”の違いかもしれません。
本記事では、小児理学療法士としての視点から、感覚統合の違いに気づくチェックリストや、家庭でできる支援のヒントを紹介します。
感覚統合とは?〜“感じる力”が動きの土台になる〜
感覚は「受け取る」だけでなく「整理する」力が必要
私たちの身体は、次のような感覚を同時に使って動いています:
- 前庭感覚(バランス・揺れ・スピードの感覚)
- 固有受容覚(関節や筋肉の動きを感じる感覚)
- 触覚(皮膚からの刺激)
- 視覚・聴覚(目・耳から入る情報)
これらを脳がうまくまとめて使う力が「感覚統合」です。
この力が育っていないと、動作がぎこちなくなったり、場面に合った行動が難しかったりします。
家庭で気づける!感覚統合のチェックリスト
以下は、家庭で「もしかして…?」に気づけるヒントになるチェックリストです。
あくまで“傾向”を見るもので、「多いから問題」と決めつけるものではありません。
【感覚統合チェックリスト(30項目)】
- すぐ転ぶ・つまづくことが多い
- 音や光に敏感/逆に気づきにくい
- 力加減が難しい(筆圧が強すぎる/弱すぎる)
- 人に触れられるのを嫌がる
- 自分の身体の位置がわかりにくい様子がある
- ジャンプや回転が苦手 or やりすぎる
- 落ち着きがない/ずっと動いている
- 姿勢を保つのが苦手(すぐだらんとする)
- 食べ物の食感・においに強く反応する
- 新しい場所や音に過敏でパニックになることがある
- 見本を見ても真似が難しい
- リズムに合わせた動きが苦手(スキップ、なわとび)
- 洋服のタグや靴下の感覚を気にする
- 落ち着かないときに自分で揺れていることがある
- 言葉の指示だけでは行動につながらない
…など。
3つ以上当てはまったら要注意…ではなく、支援のヒントととらえてください。
「今、どんな感覚が育ちきっていないのか?」を見つけることが出発点です。
感覚の違いがある子に見られやすいサイン
感覚がうまく整理されないと、次のような“行動のズレ”が見られます。
- 力加減ができず、強くぶつかる・優しくできない
- 周囲の刺激(音・におい・視線)に敏感すぎる or 鈍感
- 特定の動きを避ける(ジャンプ・回転など)
- 人の動きを真似するのが難しい
- 体育が“こわい”と感じやすい
一見すると「わがまま」「不注意」「やる気がない」と誤解されやすいですが、
実は“感じる力”にズレがあるだけのケースも多いのです。
遊びながら整える!家庭でできる感覚あそび
発達支援の基本は「遊びの中で育てること」。
感覚統合の育ちを促すおすすめ遊びを紹介します。
前庭感覚(バランス・揺れ)
- ゆらゆらブランコ
- ごろごろ前転・でんぐり返し
- トランポリンでのジャンプ
固有感覚(身体の位置・力加減)
- 雑巾がけや手押し車
- おしくらまんじゅう・押す遊び
- 重い布団やぬいぐるみを運ぶ
視覚×身体の協調
- 風船バレー(目で追ってタイミングを合わせる)
- ボールキャッチ(大きさ・色を変えて)
- スカーフキャッチ(ゆっくり動くものを注視)
🧑⚕️みっちゃん先生のまなざし|親として見つめていること
私は、小児理学療法士として子どもたちの“発達のちがい”を見てきましたが、親としても日々実感していることがあります。
たとえば、うちの子は「耳で聞いた言葉を覚えておくこと」がとても苦手でした。
そのことに気づいてから、私は「どう伝えたら届くかな?」と試行錯誤するようになりました。
でも、“知る”ことと“対応する”ことは別の難しさがあるんですよね。
対応できるとわかっていても、日常の中ではつい感情が先に出てしまうこともあります。
だからこそ、私はチェックリストを「できる/できない」を判断するためではなく、
“その子の感じ方を知るヒント”として使ってもらえたらと思っています。
子どもに対して「なんでできないの?」と思ってしまうとき、
「これは今、感覚的にまだ難しいのかも」と一歩引いて見られるようになるだけで、親のストレスはずいぶん和らぎます。
知らないままでは、イライラも不安も募るばかりです。
でも、知っていると「今はここが育っている途中なんだ」と受け止めやすくなる。
感覚の違いに気づくことは、子どもを理解することでもあり、親自身をラクにすることでもあると私は感じています。
不安なときの相談先とサポート
気になることがある場合は、以下のような機関で気軽に相談できます:
- 地域の発達支援センター
- 小児リハビリテーション科
- 作業療法士・理学療法士のいる運動教室
- 保健センターの乳幼児健診など
「困ってから」より「ちょっと気になる」で動くことが、安心と支援につながります。
まとめ|感覚の違いは「個性」であり、支援のヒントになる
感覚統合の違いは、決して「できない子」ではありません。
その子の“感じ方”に気づき、“その子らしさ”に寄り添うことで、苦手は安心に変わります。
「できるようにする」だけでなく、
「感じる力を育てる」「安心できる環境をつくる」ことが、
本当に大切な支援につながっていきます。