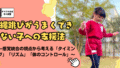~動作の不器用さの背景と支援~
■ 背景:なぜあの子は「ぎこちなく見える」の?
運動会や体育の授業、日常の遊びの中で、こんな姿を見たことはありませんか?
- ボールを投げようとすると、腕と足の動きがバラバラになる
- 走り出すと、全身が揺れたり、足元が不安定になってしまう
- ジャンプをすると、手足が固まってロボットのように跳ぶ
- 身体を動かすたびに「ぎこちなさ」や「不自然さ」を感じる
一生懸命やろうとしているのに、どこかちぐはぐ。
そんな子どもの動きを見て、保護者の方が「この子、運動が苦手なのかな?」「うちの子だけ、なんか変…?」と心配になることもあるかもしれません。
でも実は、これは「やる気がない」わけでも「運動神経が悪い」わけでもありません。
感覚の土台がまだ育ちきっていないことで、体の操作がうまくいっていないだけなんです。
子どもは日々の生活の中で、「感じる・動く・調整する」といった感覚の経験を重ねながら、自分の体の使い方を覚えていきます。
しかし、ある感覚が育ちにくい子の場合、それが「ぎこちない動き」として現れてくることがあります。
この記事では、その**「ぎこちなさ」の背景にある感覚統合の視点**をもとに、どんな感覚が影響しているのか、家庭ではどう関わればいいのかを、わかりやすく解説していきます。
やり方:ぎこちなさの背景にある“感覚のズレ”
子どもの動きがぎこちないとき、それは「動きが下手」なのではなく、
自分の体を“感じる”力や、“動かす”力のつながりがうまくいっていない状態かもしれません。
感覚統合の観点では、以下のような感覚の育ちが影響していることが多いです。
① 固有受容覚:自分の体を感じにくい
固有受容覚とは、筋肉や関節から伝わる「今、自分がどう動いているか」を感じる感覚です。
この感覚が弱いと…
- 力加減が分からず、動きが大きすぎたり小さすぎたりする
- 身体の一部を動かしているつもりが、実は止まっていたり遅れて動いたりする
- 体が「自分のもの」としてつかみにくく、動きがぎこちなく見える
たとえば、ジャンプをしても手が横にぴんと伸びたまま固まっているような子は、
体の一部を意識的にコントロールする感覚がまだ育っていない可能性があります。
② ボディイメージ:体の全体像がぼやけている
「今、自分の体がどこにあって、どうなっているか」を頭の中でイメージする力です。
この感覚が弱いと…
- 自分の体を大きく使う運動(ジャンプ・転がる・走るなど)が苦手
- 道具との距離感がつかみにくく、ぶつかりやすい
- 動きが縮こまったり、必要以上に力が入ってしまう
自分の体の「地図」がぼんやりしていると、動作のなめらかさが生まれにくくなります。
③ 前庭覚:動きとバランスの軸が不安定
ジャンプ・回転・走る・止まるなどの運動中に、体の向きやスピードを調整する感覚です。
この感覚が不安定だと…
- 動き出しに時間がかかる(“よーいドン”で出遅れる)
- バランスがとれず、ふらついたり、動きに無駄が多くなる
- 急な動きに対応できず、動きがちぐはぐに見える
特に、体幹がぐらぐらしている子は、この前庭覚がうまく働いていない可能性があります。
④ 運動の協調性:動きの“つながり”が育っていない
手足・頭・体幹といった複数の部位を、タイミングよく連動させる力です。
この力が育っていないと…
- 手と足が別々に動いてしまい、滑らかな動きができない
- 思っているように体が動かず、何度もやり直しになる
- 効率の悪い動きをして、すぐに疲れてしまう
協調運動は、体の各部分が“チームプレー”で動くために欠かせない感覚。
これがうまくいかないと、ぎこちなさがより目立ってきます。
🔍 見るべきポイントは「できる/できない」ではなく、「動きの質」
ぎこちない動きの背景には、感覚の未熟さが隠れていることが多くあります。
単に「この動きができたかどうか」ではなく、
- 体全体がどう使われているか?
- 無駄な動きや不安定さはあるか?
- 繰り返しの中でスムーズさが生まれてきているか?
こうした“動きの質”に注目して、子どもの動きの背景を見つめてみましょう。
感覚と運動支援に関してはこちもチェック✅
運動が苦手な子の支援
工夫:家庭でできる観察&支援アイデア
ぎこちない動きの背景には、「感覚のつながりがうまくいっていないこと」があります。
つまり、本人が“うまくやろうとしているのに、体がついてこない”という状況です。
そんな子に対して、家庭でできる支援は、「感覚を取り戻すような遊び」や「動きの整理ができる経験」を与えること。
ここでは、特に効果的な3つの遊びとそのねらいを紹介します。
① クマ歩き|体の感覚を全体で“感じる”体験に
両手・両足をつけて床を歩く「クマ歩き」は、
体幹の安定、バランス、全身の筋肉感覚を同時に刺激できる、とても有効な運動です。
特に、
- 手足の動きがバラバラな子
- 上半身と下半身の動きがつながらない子
- 動きがフラフラして安定しない子
にはおすすめです。
最初はぎこちなくてもOK。
「前にまっすぐ進めてるかな?」「手と足がバラバラになってないかな?」と、保護者が声をかけながら一緒にやってみることで、感覚が整理されていきます。
この遊びで育つ力:
- 固有受容覚(筋肉の感覚)
- 前庭覚(バランス・体の向き)
- 協調運動(手足の連携)
② ゆっくり転がる|自分の体を“感じる”時間を
仰向けからうつ伏せへ、またはその逆へ、
「ゆっくり転がる」動きは、自分の体の重み・向き・動きの順番をじっくり感じる経験になります。
ぎこちない子どもほど、早く転がったり、ゴロンと雑に転がってしまいがち。
それをあえて“ゆっくり転がってみよう”と誘導することで、
- 「今どこが床についているのか?」
- 「次はどこを動かせばいいのか?」
を自然と感じるようになります。
この遊びで育つ力:
- ボディイメージ(体の位置と全体像)
- 固有受容覚(力加減と順序)
- 前庭覚(回転と重力の感覚)
③ 両手タッチゲーム|左右の“つながり”をつくる
「右手で左膝をタッチ!」「両手で太ももタッチ!」など、
身体のいろんな部分をタッチする動きは、左右の協調性や身体イメージの整理に効果的です。
とっさに動くと、ぎこちない子は…
- 間違った手を出してしまう
- 体のどこを触ればいいか分からず、時間がかかる
- 動きがカクカクしてしまう
という反応が見られます。
でも、遊びとして続けていくと、だんだん体の地図が頭に描けてくるようになります。
この遊びで育つ力:
- 協調運動(タイミングと左右の連携)
- ボディイメージ(体の部位認識)
- 前庭覚・固有受容覚の同時統合
🔍 見るべき視点は「少しずつ整っていく動き」
できる/できないよりも、
- 動きがスムーズになってきているか?
- 一度できた動きが再現できるようになってきたか?
- 自分から「もう一回やる!」と言ってくるか?
そんな“小さな変化”に気づいてあげることが、次の支援のヒントになります。
まとめ:ぎこちない動きの先にある“育ち”
子どもの動きがぎこちないとき、私たちはつい「もっと上手に動いてほしい」「なぜできないの?」と感じてしまいがちです。
でも、その裏には“感じづらさ”や“つながりにくさ”があるかもしれません。
体の地図がぼんやりしている、力の加減がうまくいかない、動きの順番が混乱している…。
そんな“感覚の育ち”が追いついていない状態が、ぎこちない動きとして現れているのです。
支援のカギは、「できるようにさせる」ではなく、
“少しずつ整っていく体の感覚”に寄り添うことです。
- ぎこちない動きの意味を知り
- 日常の遊びの中で感覚を育て
- 「できた!」の芽が出てくるのを一緒に見つけていく
そんな関わりが、子どもの“からだの自信”を育てていきます。
焦らず、比べず、できることから。
親子で一緒に、楽しい体の冒険を続けていきましょう。
📚 参考文献
- 佐藤哲史・森田哲史(2021)『感覚統合と運動感覚の教科書』秀和システム
- Ayres, J. (2005). Sensory Integration and the Child. Western Psychological Services.
- 文部科学省『学習指導要領(体育)』https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/01/19/1234931_010.pdf