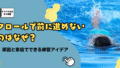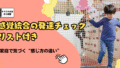はじめに
「最近、運動が苦手そう…」「バランスが悪い気がする」
そんなふうに感じることはありませんか?もしかすると、その背景には**“感覚の育ち”**が関係しているかもしれません。
子どもが身体をうまく動かせるようになるには、「感じる力(感覚統合)」が土台になります。
そしてその力は、特別な運動ではなく、**家庭の中でできる“遊び”**を通して伸ばしていくことができるのです。
今回は、感覚統合の考え方をベースにした「家庭でできるあそび」を年齢別にご紹介します。
ぜひ、今日から遊びの中に取り入れてみてくださいね。
感覚統合は“あそび”で育つ
感覚の違いは「できない」のせいじゃない
運動が苦手そうに見える子どもは、筋力や運動神経だけでなく、「感じ方」が影響している場合があります。
たとえば、ジャンプが怖い・バランスがとれない・力加減が難しい…そんなときは、前庭感覚や固有感覚の未発達が関係していることも。
遊びが“脳と身体”のつながりを育てる理由
感覚統合とは、視覚・聴覚・前庭・固有感覚など、複数の感覚を脳で整理し、体を動かす指令に変える力のこと。
この力は、大人のような運動トレーニングよりも、遊びを通じて自然に伸ばすことが効果的です。
家庭での遊びが効果的な3つの理由
- 安心感がある:リラックスして感覚を感じやすい
- 繰り返しやすい:好きな遊びなら何度でもできる
- 生活に密着:毎日の中で“感じる”経験が積める
年齢別!感覚統合を育てる家庭あそび
3〜4歳「まずは感じて動いてみる」
- くるくる回転遊び(前庭覚)
- お布団ぐるぐる巻き(触覚・固有覚)
- 転がしあそび・前転ごっこ(重力に逆らう感覚)
- 風船たたき・フワフワボール遊び(視覚・力加減)
5〜6歳「バランス・力加減を育てる」
- クマ歩き・ワニ歩き(体幹・固有感覚)
- イス渡りジャンプ(バランス・前庭覚)
- 手押し車・雑巾がけ(支持力・協調運動)
- ジャンケンリズムジャンプ(タイミング・順序)
小学校低学年「動きをつなぐ・順序立て」
- バスタオルで引っ張り合いゲーム(重心移動)
- ボールリレー・バケツキャッチ(空間把握・協調性)
- ストロー吹きレース・反応ゲーム(口の固有感覚・視覚反応)
- あやとり・紙飛行機競争(手先の順序動作)
声かけ&取り組み方のコツ
うまくできなくても「楽しかった?」を大切に
感覚の遊びは“できるかどうか”よりも、「感じたかどうか」が大切です。
「正解」より「感じたこと」を拾ってあげよう
「怖かった?」「グラグラしたね」など、感じたことを一緒に言葉にしてあげましょう。
5分でもいい、日常に“感じる時間”をつくろう
毎日続けることが難しければ、週末だけでもOK。
継続のコツは**「ルール化せず、なんとなく遊びの中に混ぜること」**です。
🧑⚕️みっちゃん先生のまなざし|「今できること」に縛られすぎないで
こんにちは、小児理学療法士であり、子育て中の親でもあるみっちゃん先生です。
この記事では年齢別にあそびをご紹介しましたが、「この年齢ならこれができるべき」とは思っていません。
むしろ、子どもによっては「5歳でも前庭感覚は3〜4歳相当」ということもあります。それは“発達のばらつき”であり、その子の個性として見てあげてほしいのです。
理学療法士としても、親としても、「今この子が、どの感覚をどれだけ使えているか?」を見つめることを大切にしています。
だからこそ、「できたかどうか」ではなく、「今日は楽しめた?」「気持ちよく動けた?」という問いかけを、これからも大事にしていきたいと思っています。
保護者が知っておきたい“感覚の個性”
- 「服を嫌がる」「回転が好き」などの行動は、感覚の過敏/鈍麻のサインかもしれません
- 感覚の特性に気づくことは、苦手を責めずに“その子らしい遊び”を見つけるきっかけになります
- もし「なんとなく気になる」状態が続く場合は、小児リハビリや発達支援の専門家に相談してみるのも選択肢の一つです
まとめ|遊びは“感じる力”のトレーニングになる
運動が苦手な子どもも、“感じる力”が育つと、自然と「動きたい」「やってみたい」という気持ちが芽生えます。
家庭の中で「ちょっとおもしろいあそび」を取り入れるだけでも、十分に感覚統合のサポートになります。
焦らず、楽しく。
子どもが“自分の身体と仲良くなる”ための時間を、一緒に過ごしていきましょう。
🔗 関連記事・あわせて読みたい
- 5歳で育てたい運動能力とは?片足立ち・スキップができる子の特徴
- 6歳で伸ばしたい運動能力 発達目安と遊び方
- 7歳で差が出る運動能力とは? バランス感覚と協調運動の伸ばし方
- 8歳で伸ばす球技の力 苦手克服と敏捷性アップの運動法
📘 参考文献:
- 柳田信也ほか『脳神経科学・発育発達に基づく体育・運動指導の理論と応用』(大修館書店)
- 宮田卓樹・山本豆彦『脳の発生学』(化学同人)
- Gallahue, D. L.『Understanding Motor Development』(日本版参考)
- 加賀谷淳子ら「敏捷性トレーニングの学年間効果に関する研究」(発育発達学会誌)
🔗 参考サイト:
- 一般社団法人 日本感覚統合学会(https://www.jsid.org/)
- こども発達支援研究センター(https://www.child-support.org/)