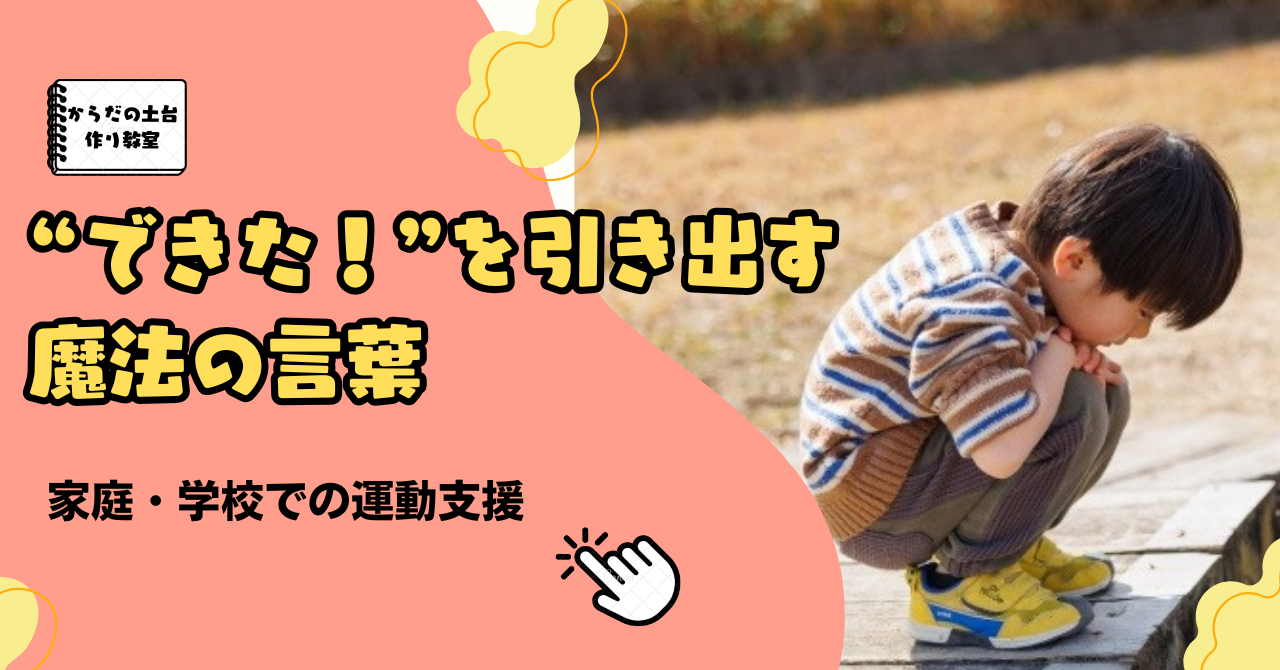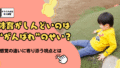はじめに|がんばってるのに動けない…その子にかけるべき言葉とは?
「どうして動けないの?」「もっとちゃんとやって!」
つい、そんな言葉をかけてしまうこと、ありませんか?
運動が苦手な子にとって、体育や運動の時間は「できない自分」と向き合うプレッシャーの時間。
実は、“声かけ”ひとつで、子どものやる気も自信も大きく変わるのです。
本記事では、小児理学療法士の視点から、運動が苦手な子どもに響く**“魔法の言葉”**を具体例とともにご紹介します。
「できない」子にかけがちなNGワード/なぜ効かない?
よかれと思って言った言葉が…逆効果になることも
- 「もっとがんばって!」
- 「ちゃんと見てごらん」
- 「お兄ちゃんはできたのに」
- 「どうしてできないの?」
これらの言葉は、無意識に**“比べる” “責める” “急かす”**メッセージとして伝わることがあります。
特に感覚統合の未発達や運動協調性が育っていない子にとって、「わかっていても動けない」ことは多々あるのです。
“できた!”を引き出す声かけ|3つのポイント
① 結果より「気づき」をほめる
✔「今日はボールをよく見てたね」
✔「足がしっかり地面についてたよ!」
✔「最初よりジャンプが高くなってきたね」
👉「勝った・できた」よりも、“本人が気づいていない変化”を言葉にすることが、自信に繋がります。
② 動作を言語化して「自分の体に注目」させる
✔「今、どこに力が入ってた?」
✔「さっきより、腕の振りが大きかったね」
✔「どうやったらうまくいったと思う?」
👉身体の感覚や動きに意識が向くことで、「できた感覚」が記憶に残りやすくなります。
③「〇〇できたね」より「〜しやすくなったね」
✔「前より、まっすぐ走れるようになってきたね」
✔「ジャンプが前よりしやすくなった感じ、あった?」
👉「できる/できない」の二分法ではなく、「変化のプロセス」に注目した声かけが子どもを前向きにします。
状況別|こんなときどう声をかける?
📌 体育で泣いてしまったとき
❌「泣かないの!」 → ✅「びっくりしちゃったね。気持ち、教えてくれてありがとう」
→まずは“感情を認める”ことで、心を整える土台に。
📌 運動会でうまくできなかったとき
❌「もっと練習しなきゃ」 → ✅「ちゃんとゴールまで行けたこと、すごくない?」
→うまくできた“部分”に注目し、自己肯定感を守る声かけを。
📌 家庭で練習してもうまくいかないとき
❌「何回言ったらできるの?」 → ✅「どうすればやりやすいか、一緒に考えようか」
→親も“並走者”になる姿勢を示すと、子どもは安心します。
🧑⚕️みっちゃん先生のまなざし|声かけにこそ“寄り添う感覚”を
声かけって、本当に難しいものです。
つい感情的になって、言いたくない言葉が出てしまうこともある。
でも、私はこう思っています。それでもいい。むしろ「やってみること」に価値があると。
もしキツい言葉をかけてしまったとしても、
あとで「ごめんね」と言ってギュッと抱きしめるだけで、十分に伝わるものがあるんです。
「もう言っちゃったからダメだ…」と自分を責めるよりも、
次に優しい言葉を選んでみる。それだけで子どもとの関係はきっと変わっていきます。
もちろん、できるだけポジティブな言葉を選んでほしいし、
「できたね!」の一言が、子どもにとってどれだけの勇気になるかも知ってほしい。
でも、完璧じゃなくて大丈夫。
大切なのは、“言葉でつながろうとする姿勢”そのものなんだと私は思います。
まとめ|「できることを増やす」より「感じられる安心を」
声かけは「育てる言葉」であり「守る言葉」でもあります。
運動が苦手な子どもにとって、
その言葉があるだけで「安心してチャレンジできる空間」になります。
- 結果ではなく、変化に気づく
- 行動だけでなく、気持ちを認める
- 無理に励ますより、一緒に考える
“できた!”を引き出すのは、技術よりも「言葉のぬくもり」かもしれません。